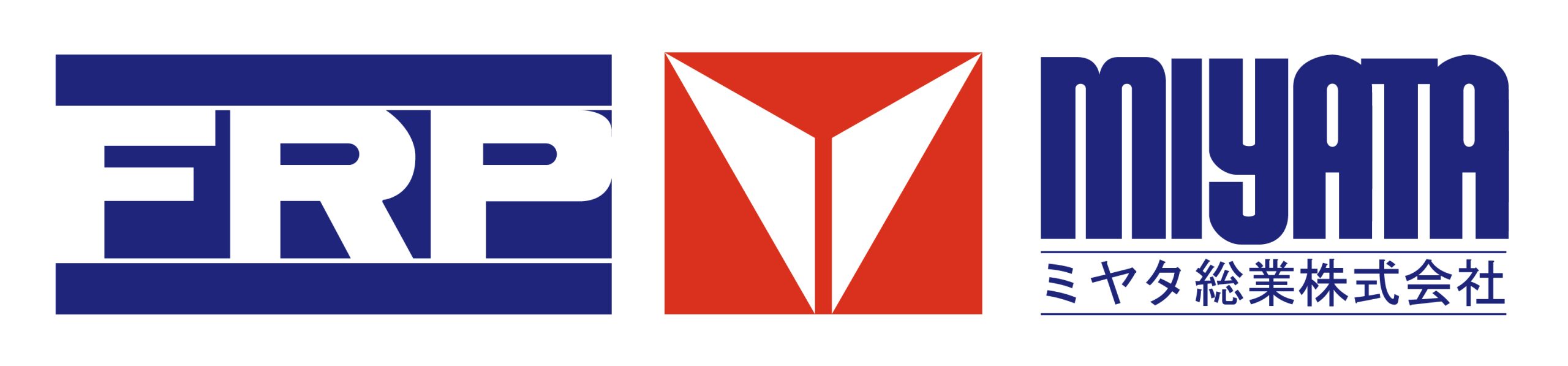グラスファイバー弓とは何か
竹弓に対して、グラスファイバー弓は省略して「グラス弓」と呼称されていますが、弓本来の性質を表す、「竹弓」の対義語としての正確な表現では、「FRP(エフアールピー)弓」と言います。まず竹弓は、ヒゴと呼ばれる竹を素材にした芯 […]
弓射におけるエネルギーの法則と弓具の破損について②
弓射と弓具の破損の関係については、西洋のアーチェリーと和弓で、全く状況が異なります。それは西洋アーチェリーの弓と和弓の構造・成り立ちを比較する事で、和弓においては破損しない為に何に気をつけなければならないのか、非常によく […]
弓射におけるエネルギーの法則と弓具の破損について①
弓道に限らず弓射の物理現象は、矢を弦につがえて弓を引いた分、湾曲した弓が元の形に復元しようとする力の位置エネルギーである弾性位置エネルギー(potential elastic energy)を持つことに始まります。それが […]
手の内の働きと弓の握りの太さ
射法八節の前身である「五味七道」の時代は、「手の内は射の総決算」と言われるくらい、手の内の重要さが強調されていました。それは、弓手の最後の働きで弦枕から弦を外すほどのひねりを加える角見の働きは、以下の記事でご説明したとお […]
【新発売】A型 白木竹弓風
ミヤタが当初発売したグラスファイバーFRP弓は、張った直後から弓が引け、初心者にも取り扱いしやすく性能良い弓、という評価をいただき、主に学生弓道部を中心に普及していきました。 その後、高段者、師範の方々にもその性能を評価 […]
堂射で極まる弓手起点の離れとそれを支える新弓具、及び射の基礎となる伝統の骨法
江戸時代に三十三間堂にて行われた堂射は、弓道の射法が極限まで磨かれ、その射に応えるべく最先端の弓具が開発された時代でした。現代まで使われているそれらの弓具の仕組みを、射法・射術の物理現象の視点から考察すると、弓道の射法や […]
弓道の取りかけ(蒙古式取りかけ法)、古来の弓射の取りかけ(原始的取りかけ法)、西洋の取りかけ(地中海式とりかけ法)の長所と短所
明治時代、東京帝国大学(現在の東京大学)の客員教授として日本に滞在し、大森貝塚を発掘し、日本の考古学・人類学の先駆けとなったとされるアメリカの考古学者・動物学者のエドワード・S・モース博士、という学者がいました。モース博 […]
握りの位置と弓把について
弓把は握りの上の位置で弦との距離を五寸程度(約15㎝)に張る、と一般的に言われていますが、その目的は弓把を高く、弦を弓がピンと張った状態に保つことで、弓射による弓の破損を防ぎ、かつ弓射のパフォーマンスを良くすることにポイ […]
那須与一に挑戦(1983年フジテレビ「 小川宏のなんでもカンでも!」出演)
今から40年程前の話ですが、フジテレビのテレビ番組「小川宏のなんでもカンでも!」という科学や歴史等をテーマにしたクイズ番組がありました。日常生活で起きる様々な現象や歴史的事実をテーマにした実験・検証を行い、その結果を予想 […]
弓の性能と耐久性の関係
浦上栄先生の著書「紅葉重ね・離れの時機・弓具の見方と扱い方」(弓道範士十段 浦上栄 著 浦上直・浦上博子 校注)の「弓具の見方と扱い方 第五節 弓の性能」の説明によると、鋭い反発力と矢飛びの良い弓と、丈夫な弓は両立しない […]
弓手起点の離れと堅帽子のゆがけ
第24回世界弓術選手権大会(World Archery Championships 1967)は、宮田純治にとってグラスファイバーFRPの和弓を開発する契機となった他、もうひとつ非常に重要な発見がありました。それは、本大 […]
ミヤタのグラスファイバーFRP弓、一般弓道用として発売
1967年(昭和42年)当時の弓道環境は既に現在のように、武士が職業として弓を引く時代ではなく、学生の部活動や、趣味として弓を引くことが主流の時代になっていました。 弓には強い部分と弱い部分があり、竹弓では1張の弓ごとに […]
西洋伝統の弓射・弓具と現代アーチェリーの関係にみる伝統弓道・弓具の将来
World Archery Championships 1967において、各国選手が使用していたアーチェリーの弓は、大半が既に米国製のグラスファイバーFRPのリムを使用した新型の弓で、矢もほぼ100%がジュラルミン矢と、 […]
World Archery Championships 1967 グラスファイバーFRP製和弓の挑戦
1967年6月25日、オランダ アメルスフォートで開催されたWorld Archery Championships 1967の第一日目が、開会式の後、昼近くから競技が開始されました。晴天には恵まれたものの風が強く、波乱を […]
世界初グラスファイバーFRP製の和弓の誕生
前述した様々な弓具研究を経て、90mの遠距離弓射においても鋭い矢勢と高い的中精度を併せ持つ性能の和弓を実現する為、また常に安定した状態を保ち雨天にも強い、という性質を同時に和弓にもたせる為、既にアーチェリーの弓で使用され […]
World Archery Championships 1967に向けた弓具研究③ 矢、ゆがけ、弦
矢は、以下の矢を、ジュラルミン矢含め、矢師の曽根正康先生が製作してくださいました。 矢 ・竹矢(一文字、麦粒、竹林[堂射用の矢]:曽根正康作) ・ジュラルミン矢(シャフト:イーストン製) 当時イーストン製のシャフトのジュ […]
World Archery Championships 1967に向けた弓具研究② 弓
「遠的における和弓弓具研究の一端として」のレポートで、以下の弓の実際に使用しその特徴をまとめ、World Archery Championshipsに適しているのはどういう性質・性能の弓なのか、宮田純治は徹底的に研究しま […]
World Archery Championships 1967に向けた弓具研究① 総括
World Archery Championships 1967の前年に開催された遠的強化合宿で行われた遠的競射会(アーチェリールール)において、宮田純治は和弓部門第1位、アーチェリー混合部門でも第4位という成績を収めま […]
World Archery Championships 1967に向けた遠的強化合宿
1967年の世界弓術選手権大会(World Archery Championships 1967)を見据えた遠的強化合宿を全日本弓道連盟が主催し、全国からアーチェリー・和弓の選抜選手が集められました。 選手の条件は、下記 […]
全日本弓道連盟による第24回世界弓術選手権大会(World Archery Championships 1967)への和弓選手派遣
1964年(昭和39年)の東京オリンピックおいて、アーチェリーが正式種目となる予定(実際にはエントリーが少なく1972年のミュンヘンオリンピックに延期)で、その当時は弓道・アーチェリー双方の国際競技への選手派遣の参加権は […]