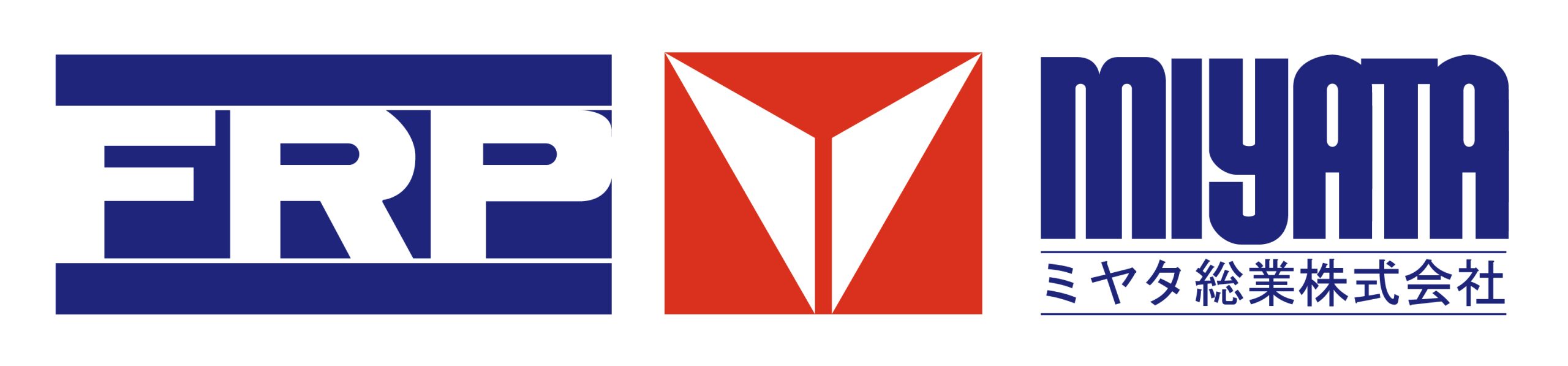手の内
手の内は、弓手起点の離れを実現する為に、極めて重要な要素であると同時に、実は弓具を傷めず壊さずに引く為にも、非常に重要な要素になります。正しく手の内を作った状態で引き分けから弓が正しく右方向に捻(ひね)ることができてないと、特にデリケートな性質を持つ竹弓において、竹弓の胴が抜ける(弓の疲労が激しく竹が張力を失い、ダランとした成になり使用できなくなる)、こうがいおきが起きてしまう、弓が部分的に破損する、折れる等の故障にもつながる場合があります。
なぜ手の内と弓の故障が関係あるのか、というのは、手の内ができて引き分けから弓全体が適切に右側に捻られていればこそ、その捻りにより弓にかかる力が弓全体に分散され、弓返りによってその力が余すところなく弦から矢に伝わる為、弦、弓に余計な衝撃を与えずに、弓具を傷めずに引ける為になります。ベタ押しの手の内のように、それらが実現できない弓射で弓を引くと、弓への力のかかり方が1点に集中しやすく、さらに馬手離れによる離れの振動が強くなり弓具に与えるダメージが大きくなります。
宮田純治は、手の内の指導の時、ベタ押しの状態は、弓を針金にたとえ、針金をポキっと折るようにして弓を引いているようなもの、と指導していました。つまり、弓が適切に捻れていない為に弓にかかる力が分散されず、弓の力が1点に強くかかってしまったり、竹弓では竹の疲労が更に激しくなり、胴が抜ける、こうがいおき等が起こるリスクを増大させる要因となります。また弓には強い部分と弱い部分があり、弊社のグラスカーボン弓でも、FRPの物理特性から胴が抜ける、こうがいおき等と同じ故障は起きないものの、硬い弦を使用していると弓が衝撃を受けた時に弦が切れずに弓にダメージが行き、弱い部分から弓が破損してしまう、といった故障がおきることがあります。また、この弓の捻りは、正しくは大三からの引き分けから捻るもので、引き分けている分、弓に引く弓力分の張力が、引き分けと同時に段々にかかって弓全体に適切な力がかかりますが、正面打起し等で打起しから大三に至る時に勢い余って大三で弓を強く捻ってしまうと、弓に張力の負荷がかかってない為に弓が捻りやすく、引き分け前に弓に部分的な大きな負荷がかかり、弓の成がおかしくなってしまう場合もあります。
では、どのような手の内ならば、鋭く大三から弓を右方向に捻れるのでしょうか。
以下は、宮田純治の実際の手の内の整え方になります。日置流の斜面打起しの手の内の整え方ですが、斜面打起しの最大のメリットは、手の内を完全に整えてから打ちこすことができて、大三で引き分けがスタートする形と全く同じ形に整えてから打ち起こせる点にあります。大三からは同じような射手の動作・弓具の働きになる為、日置流の完成形の手の内を確認しておくことは、流派を問わず参考になるかと思います。

鵜の首、という鳥の形に例えた親指を下に向けた形で、握り革の右側から7:3の割合に虎口(人差し指と親指の間の部分)を当てる。虎口の当て方の配分から非常に重要なポイントで、右寄り過ぎれば手の内が内竹の右側に入りすぎ、引き分けで弓を捻る表面積が小さく鋭く捻ることができず、逆に左寄りに控えすぎれば、大三で力が適切に入らず弓がうまく捻れない、といった問題がおきます。この7:3の割合が最も鋭い角見を利かせ弓を捻ることができるという、昔の武士が試行錯誤の研究の末にたどり着いた最適な虎口の当て方、になります。そもそも「角見」という言葉は、この弓への虎口への当て方からきており、昔の伝統の竹弓は現在の標準的な弓よりも、握りの内竹部分に外竹側からの側木の傾斜がついていた為内竹の幅が狭く、7:3の割合で虎口を当てると、内竹の角に虎口の中心がくる為、「角見」と称されました。この使用する弓の全体的な握り幅が細くなると、この70パーセントの捻る部分の内竹の表面積が物理的に小さくなり、特に弓の弓力が強くなるほど鋭い角見が利かせにくくなる為、宮田純治は射法上、その弓本来の標準の握り幅より細いものは、一般的に推奨していません。これは上記手の内の働きの物理現象と一致した見解になっています。ただ本来の弓の幅は、弓本来が持つバランスによって決まっています。

掌の天文筋(掌の一直線の筋)を外竹部分の左角につける。これが非常に重要なポイントで、ついてないと弓を力強く捻ることができない。親指が鵜の首で下に向いている事も、手の皮がギリギリと弓に巻きつくようにして弓を支えるのに重要な要素であります。

小指、薬指を上側に詰めて小さくととのえ、中指は差し込むように入れる。この3本の指は縦に一直線に揃って整える。このような手の内の整え方を「紅葉重ね」と言いますが、小さく作ることも、鋭い角見を利かせる大事なポイントになります。上記完成形の手の内の形を見てもわかる通り、弓はこの3本指では弓は握りこまず、ふわりと添えている程度になります。引き分けで、3本の指の先が白くなると、力が入りすぎ、と宮田純治は指導しています。3本は添えている程度である為、指の長さはそれほど関係なく、弓が太くても親指の付け根と天文筋がついた掌で、弓はしっかりと支えられます。この時、虎口の下には空洞ができていなければならず、ベタっとくっついていると、鋭く弓が捻れません。

上記が、横から見た手の内の完成形。目視はできないが、しっかりと外竹の左角に天文筋がついており、人差し指、中指、薬指、小指には余計な力が入らず、親指はまっすぐにピンと張られて下方を向いている。虎口の下には空洞が空いている。この形が、大三・引き分けにおいても維持されなければならない。手の内が崩れていると、引き分けで親指が曲がってしまい弓を捻る力が入らないことがあります。人差し指に力が入りつっぱったりすると、弓を捻る力が減衰されてしまいます。またこの親指の形は鵜の首、と鳥の首の形に例えた形で、上押で押しているわけではありません。この形で大三から中押しで真っすぐ押すと、力強く弓が右方向に捻れます(浦上栄先生は、離れの際に軽い上押を加味して弦枕から弦を外すように指導していたようです)。中指、薬指、小指に力を入れてはいけないのは、せっかく弓を捻って弓返りする働きに、その3本指で弓返りに指と弓の握りとの摩擦でブレーキをかけてしまう為になります。弓返りしても3本の指が開いてしまう場合は、やはり力が入っている為になります。宮田純治の手は成人男性のなかでは小さめですが、添付写真の28mmの握り幅の弓は伝統の弓と比べても特段太いものではなく、なんなく握れて鋭い角見を利かせることができています。もちろん、これ以上の握りの太さの弓においても同様になります。
このように弓の握り方ひとつにおいても、手の内のように長年にわたる射手の研究・試行錯誤の結果の最適解が、既に長い弓道の歴史にあります。
5本しかない指で、指4本に力を入れない、というのは人間の直感に反した弓を握る力の配分になり、弓道に入門してこの手の内を正しく教わったとしても、最初は本当にこの握り方で大丈夫なのか、とあまりにも心もとない印象を持つものです。余計な力をいれるな、と言われても、どうしても手の内が引いているうちに崩れてしまう、ぎゅっと弓を握り力が入ってしまう事が、どうしてもあります。その為、この正しい手の内の習熟には、非常に長い年月がかかると言われ、手の内に定評のある日置流でも「手の内10年」、と言われています。そもそも、世界のほとんどの弓矢は短い弓で短い矢を、馬手でリリースすることで引くもので、入門者でもとりあえず直感的に弓を引けますが、和弓は長弓で長い矢を、自分の顔を超えた矢束で弓を引き、角見の働きで弦枕から弦を外し、弓手で弓返りさせて矢を真っすぐに飛ばす、という人間の直感的な引き方とは異なる、その弓具の特性を生かした後天的な技術を基礎から叩き込むところが、最初の弓道のハードルが高いところになるかもしれません。
しかし、一度でも正しい手の内ができた射手は、大三にうち起こした時に手の皮がギリギリと内側に巻き込まれ、親指以外の指4本に力を入れていないのに、天文筋についた手のひらと親指で手はガッチリと弓を支えている不思議な感覚を味わったことがあると思います。これが正しい手の内であり、正しい形ができていると、無理に大三から弓を捻らずとも、手の皮が弓に巻き付いている状態で既に弓の捻りの準備ができています。引き分けで角見をきかせていくときに力強く弓が捻れている感覚を覚え、弓手起点で離れることができた時に、今まで馬手離れで引いていた時とは比べ物にならないほどの鋭い弓返り、鋭い矢勢で真っすぐ矢が飛んでいき的中する様をみて、「これが正しい手の内なのか」と実感したことがあるのではないかと思います。
このような正しい手の内により、宮田純治は、3㎝を超える太い握り幅の30kgを超える竹弓の強弓を用い、遠矢のような極限まで箆を細くして付いているか付いていないか程度の極小の矢羽根をつけた矢でも、麻弦、細い竹矢の遠矢、竹弓の強弓等の弓具を破損せず、真っすぐに矢を飛ばすことができました。古来の堂射の射手は、寸弓と呼ばれる、握り部分の弓の厚みだけで30mmあるような、弓の幅も幅広く太い強弓(七分[21mm]の厚みの竹弓で推定30数キロ~40キロの弓力)をひきこなせたのも、これらの正しい手の内が非常に重要な役割を果たしたようです。
弓力の強い弓を引く場合も、筋力トレーニング等により腕力・背筋力がつき引き分けで会にまでは至るかもしれませんが、結局最後はこの手の内の働きにより弓手起点の離れを実現できねば、馬手離れにより強めの弓の弓力と重く安定した箆、または振動吸収性の高い箆の性質により矢を真っすぐ飛ばすことになります。それはやはり弦、弓、矢に大きな負担をかけることになります。
もちろん手の内さえできれば全てが解決するわけではなく、基本の一つではありますが、手の内は弓手起点の離れを実現する最も重要な要素である為、「手の内を見せない」というような非常に重要な事のたとえとして、日常に使われる日本語にもなったようです。
初心者のうちから正しい手の内で弓を引く事は非常に難しく、練習・稽古の最中に弓具をなるべく傷めないよう、使用する弦は麻弦・合成繊維の弦はなるべく柔らかく標準的な太さの弦を使う事で、弓に与えるダメージを軽減することができます。
「正しい」という表現は、とらえ方により一方的でそれ以後の創意工夫を認めないような高圧的なイメージをもたれる方もいらっしゃるかもしれませんが、「弓道の正しい射法」として「正しさ」が用いられてる場合、大抵はどちらかといえば西洋の概念の「ベスト・プラクティス」に近いイメージになります。ベスト・プラクティスとは、「研究開発・試行錯誤等を経て、結果として最適と実証されたやり方」になります。長年射手である武士が研究し、たどり着いたベストな弓射の実態に基づく最適解のひとつが、この「正しい手の内」であります。
弓道教本に掲載されている射法訓(吉見 順正[台右衛門])は、原典の後段の抜粋が記載されておりますが、原典では、前段部分は要約すると以下のような内容が記載されています。「押引自在の活力を有する弓矢をもって静止不動の的を射抜く、これは簡単そうに見えて少しの機微に千種万態の変化がでて、なかなかに中らないものである。朝できていたのに夕方できなくなってしまったことを的のせいにしても的は動かないものだし、弓矢のせいにしても弓矢は無心にして無邪である。だだ自省し、技を練り励むしかない。」そして後段では、では理想的な弓射をするための射法とはどのようなものか、を具体的に解説するパートになっており、「正技は(射法は)、弓を射ずして・・・」と弓道教本でおなじみの射法解説がされています。このように「正技」、「正しい技」の使われ方は、ベスト・プラクティスとして試行錯誤の末にたどり着いた射手の叡智の結晶、として用いられており、弓道を学ぶ中で得られる温故知新、なのではないかと思います。宮田純治が浦上栄先生に指導を受けていた時も、先生は門下生に対し、「(色々な創意工夫は)基本ができてからおやりなさい」と指導していたそうですが、それも先人の射手の叡智よるベスト・プラクティスが、既に歴史の長い弓道にはあるからではないか、と思われます。
弓道の弓具は、弓には、七尺三寸を標準とした弓長、入木の成、握りの位置、また矢の長さ・矢羽根、弦枕のついた堅帽子のゆがけ、その他様々な制約条件があり、射法・射術や弓具に創意工夫をするにしても、過去に積み上げてきた射法・射術・弓具の歴史があり、アーチェリーほど弓具の改造の自由度が高くありません。その制約条件の中で培われてきたベスト・プラクティスは、やはり学ぶ事が多く、まっすぐに矢を飛ばすために、弓具を傷めずに自身も安全に引くために、弓具製作者の立場からみても、非常に重要な事と思います。
ちなみに、日置の射法で「打ち切り」という弓返りを向弦程度に途中で止める、戦場で矢継ぎ早にかけるための射法がありますが、これは「三日月掌」という手の内で人差し指の先と親指の先をくっつけた三日月形の手の形で、人差し指と親指と弓の握りとの摩擦で弓返りを止めるもので、矢勢を活かしたまま弓返りを止める為に、やはり中指、薬指、小指には通常の手の内同様、力を入れずに添える程度にしておきます。逆に、打ち切りの手の内で引いているのに弓返りしてしまうと、離れで弓手を緩めている等の手の内の問題がある事が多く、宮田純治は手の内の問題の矯正に打ち切り射法で引かせることもあります。
上記は、主に宮田純治が習得した日置流の手の内の整え方に準じていますが、大三からは流派に限らず射手の動作や弓具の働きの物理現象はほぼ同じである為、和弓の弓具・弓道全体の視点からも、参考になるかと思います。
弓道教歌に「当流の 弓の雑談あるならば こころにかけて 聞きとめよかし」と言う歌があります。このように「なんらか弓のトピックについて聞き及ぶことがあれば、それは何事によらず心に留めておくと、いつか役に立つことがあるだろう」、という教えも昔からあるので、宮田純治が身に着け、指導してきた事がひとつの弓道トピックとして、射手の皆様にお役立ちになる事があれば幸いです。
(出典)
「射法訓」 吉見 順正(台右衛門)