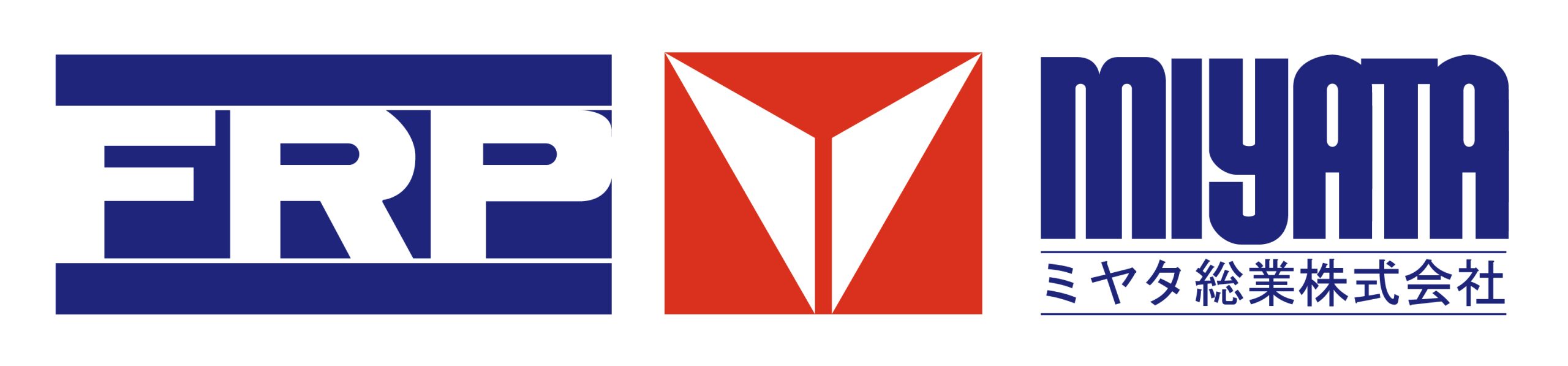堂射で極まる弓手起点の離れとそれを支える新弓具、及び射の基礎となる伝統の骨法
江戸時代に三十三間堂にて行われた堂射は、弓道の射法が極限まで磨かれ、その射に応えるべく最先端の弓具が開発された時代でした。現代まで使われているそれらの弓具の仕組みを、射法・射術の物理現象の視点から考察すると、弓道の射法や弓具がどのようにしてそのような方向で進化・洗練されていったのかが、よくわかります。
堂射の弓具として、以下のものがあり、これらは伝統の和弓、伝統の竹矢のそれぞれの能力を、極限にまで高めたものです。120mの距離を、5mの天井の高さ制限がある状態で矢を飛ばし廊下を通す、という競技そのものが、世界でも類をみない、超高難度の弓射競技になります。アーチェリーや遠矢のように仰角を上げて放物線を描くようにして120mの距離を飛ばすことですら大変なのに、5mの天井の高さ制限がある為に、それが不可能となります。つまり、放物線の着弾点を計算するような数学的アプローチができず、遠距離でも可能な限り真っすぐ飛ばさねばならず、堂射で使用する弓は、世界でも有数の強弓で引くことになります。いっぽうで和弓の弓具はデリケートで、その強弓で悪射がでて弦や弓に衝撃を与えてしまうと、自然由来のニベと竹と木で製作された竹弓、麻弦は、強弓の離れの衝撃であっという間に破損してしまう為に、超強弓を用いながら弓具を壊さずに矢をまっすぐに飛ばす弓射するという、堂射は1射1射の弓射そのものが、とてつもなく高難度の弓射となってしまいました。
それらを実現する為に、極限まで弓射技術が磨かれた事はいうまでもありませんが、弓具も従来のものでは堂射の弓射には耐えられず、様々な進化がありました。特に画期的な進化が堅帽子のゆがけで、超強弓で矢数をかけても手を痛めない目的に加えて、馬手を固定し完全な弓手起点の離れが実現するようにゆがけに弦枕と弦道がつけられ、堅帽子のゆがけが発達したものと思われます。
<使用弓>
堂射用の本番用の弓は五寸詰、稽古用に三寸詰に切り詰められた、裏ぞりを多くつけて反発力を高めたヒゴ弓(竹弓)になります。60mから120mと距離が倍になり、かつ5mの天井がある為遠矢のような仰射角をつけるわけにもいかない為、さらに弓力を強め下を切り詰め弓長を短く反発力を高めた強弓が堂射に用いられました。つまり、弓長短く、下が強い弓がより低い弾道でまっすぐ飛ぶことが、当時の弓射・弓具の研究で判明しています。もはや、西洋の地中海式射法や、東アジアの二つ掛けの蒙古式射法では引くことが不可能なレベルの強弓です。一方で素材は天然の竹、木、動物性接着剤のニベ、とデリケートな自然由来の素材のみで製作されています。その強弓がもつすさまじいエネルギーが離れで弦や弓に衝撃を与え、天然素材の短い竹弓・竹矢・麻弦を破損しないように、まっすぐに飛ばすのと同時に弓具を壊さないよう、弦や弓に振動・衝撃を与えないように確実に弓手で離れなければならない、非常に高難度の弓射でありました。
<使用矢>
竹林矢:強弓で遠くまっすぐに飛ばす為に開発された麦粒の矢(大的[遠的]に用いられた)をさらに進化させ、堂射用の超強弓の射に最適な形状に製作された竹矢。
麦粒の矢とは、矢の中心付近が太く、麦粒状に流線形の形状をした矢になります。それは、弓を引くと強い力がかかる部分が古来より経験的に知られており、その部分が太くなっている為になります。近的で使われる程度の弓力の弓では一般的な一文字でよくとも、遠的でまっすぐ飛ばす為には、宮田純治がそうしていたように、弓力は20-25㎏程度の強弓で、弓長もさらに矢勢を鋭くする為に三寸詰を使用しました。その強弓から繰り出される運動エネルギーの負荷を受ける為に、自然由来の竹矢では破損の確率が高くなり、その部分を相対的に太くすることで強化していました。一方で、一文字の矢よりも馬手離れで矢のバランスを崩しやすく、より弓手起点の弓射技術が求められます。
堂射ではそれを上回る強弓であり、すると麦粒よりも矢羽根付近によった部分が、強い力を受けることがわかり、矢羽根付近から矢尻に向け流線形に製作された矢になります。かつ、の張り(アーチェリーのスパイン、矢のしなり具合の弾性の度合い)が強く固いものになります。カーボン矢の固めのの張りとはそもそも素材特性が異なり、カーボン矢では振動吸収性の高さと復元力の高さで馬手離れのショックや蛇行を矯正しまっすぐ飛びやすいですが、竹矢ではその素材特性でその性質から、の張りの強さで弓射難度があがり、麦粒よりもさらに馬手離れで矢のバランスを崩しやすく、非常に高難度の弓射技術が求められます。
以下は、宮田純治が1967年(昭和42年)世界弓術選手権大会に参加する為に研究した、堂射用の竹林矢(曽根正康作)。麦粒よりもさらに矢羽根付近より「の」が太くなり、矢尻方向に向かってなだらかな流線形をした矢。その形状・の張り強さの為、わずかな馬手離れの蛇行であっという間にバランスを崩してしまう為、弓手の角見の働きで弦・矢の左右のバランスを保ったまま離れる磨かれた射法が求められる。弓手の角見の働きで離れることが宿命づけられた矢。

実際に、宮田純治は第24回世界弓術選手権大会に向けた弓具研究で、上記の矢師の曽根正康先生が製作してくださった竹林矢を使用した結果、少しでも馬手離れで左右のバランスを欠いた弓射となると、竹林矢がその蛇行の振動ですぐにバランスを崩してしまうのを、身をもって体験しました。一方で弓手起点で鋭い角見を利かせた際は、非常に鋭く真っすぐに長距離を通せる、その矢の性質も確認しました。最終的には、対候性その他の理由で本選にはイーストンのジュラルミンシャフトを採用しましたが、ジュラルミンシャフトは金属の素材特性で一文字でも強弓の射に耐えられる程の強度がありましたが、竹で製作された矢で強弓の射に耐えられ、まっすぐに飛ぶ矢の性質について、多くを知ることができました。
<使用ゆがけ>
堅帽子のゆがけ・・・非常な強弓を引くために、推し多め馬手三分の一の割合でも、馬手でひく力も相当な力が必要になります。もともと東アジア共通の蒙古式取りかけ法の基本形は、親指と人差し指で取りかける弓道には無い二つ掛けで、それが通常の弓道の弓射の歩射でさらに馬手の引く力が強くなる三つ掛けとなり、堂射ではさらに馬手の引く力を強くする為、四つ掛けとなりました。強弓を引く為の馬手の引く能力が上がる一方で、馬手の左右のバランスは最も悪くなり、その取りかけ法で馬手で放すと矢はまっすぐに飛ばず、強弓の離れの衝撃で弓具があっという間に破損してしまう為、弓手の角見の働きによる離れを確実に行う為に、馬手を固定し完全な弓手起点の離れが実現するようにゆがけに弦枕と弦道がつけられたゆがけ、とも言えます。
上記のとおり、堂射の120mの距離を5mの高さ制限下で矢をまっすぐに通す為に開発された、五寸詰の短い強弓のヒゴ弓、蛇行の振動でバランスを崩しやすい為、まっすぐに飛ばさねばならない竹林矢、そのバランスを崩しやすい矢を発射直前まで左右のバランスを保ち弓手の角見の働きで離れる四つがけのゆがけ、と、弓手で離れる射法を極限まで追求した弓具により、堂射の射が実現しました。日本の弓術は、馬手の左右バランスが崩れるほどに強弓を引く方向に取りかけ・ゆがけが進化した一方で、左右のバランスを保った弓手の働きで離れる射術を極限まで高めたことにより、全て自然素材の竹、木、ニベの接着剤で製作されたデリケートな弓具を用いて、強弓から放たれる弾性的位置エネルギーを余すところに矢に乗せ、「離れを弓に知らせぬぞ良き」という弓具に振動を与えない、世界に類をみない合理的な射法と弓具の関係が成立しています。世界一の強弓でありながら、同時に世界一デリケートな弓具である、細く長い竹弓、細くしなやかな麻弦、軽くしなかな竹矢を破損しないで弓射できるという、世界の弓射・弓具でも他に類をみない、非常に合理的な弓射術と弓具の調和が完成しました。
そのような弓射を実現する為に、通常、基礎の育成は長年研究され洗練されてきた骨法を基礎とした、伝統の弓射を稽古で錬成する必要があります。入江康平先生の著書「堂射」によると、大和流「矢数師資問答」の例をあげ、この極限までに高難度の堂射の弓射も、素引き(矢をつがえる素引きを含む)に始まり、骨合筋道の法に沿った基本の弓道稽古により実現しています。「まず胴づくりと肩のありようを正しくすること以外には構わず弓力の弱い弓で一日200射(矢をつがえる素引き)を10ヵ月射ると6万本の矢数になる。二年目で正しい手の内を整え、6万本、三年目にさらに射形を整え6万本、3年間で18万射」、という稽古により、正しい骨法ができるまで矢は放たずに、素引きで正しい手の内を始めとした基本を習得していたようです。正しい骨法ができるまで矢を放たないので、破損の最大の要因である離れの衝撃も無く、当然弓具も壊しません。
デリケートな和弓の弓具を破損してしまう最大の要因は、弓射による衝撃です。つまり、この古来の稽古法からもわかるように、取りかけの問題による矢こぼれやハズこぼれ、手の内の問題による馬手離れ、様々な弓射の問題のひとつひとつがデリケートな弓道の弓具にダメージを与える要因となる為、弓道の基本ができるまで、弓手で鋭く弓を捻れるようになるまで、実際には弓射で矢を発射せず、古来素引きで弓道の基本を身につける稽古が行われてきました。そのくらい、素引きは弓道の射に最適な身体の使い方を覚え矢勢よく的中良い射の基本が身につくと同時に、弓具を壊さない伝統の弓射を身につける基礎となります。当時は、巻藁前で通常の弓射のようにゆがけをつけて矢をつがえ、会の詰合に至り、十分伸合で角見の働きで弓を捻る感覚味わい、あと最後の弓手の一押しで矢が離れる前までの感覚を覚えて戻す、という稽古も素引きと呼ばれていたようです。ゆがけをつけ矢をつがえた素引きは、「留守の弓」とも呼ばれ、早気の矯正方法としても知られています。矢をつがえて実際に離れる弓射する稽古に進むのも、弱い弓力の捻りやすい弓で、長年基礎を身に着けます。
堂射ではその後、さらに実践的な巻き藁稽古に進みますが、この古来の稽古の方式を、宮田純治も弓道指導において可能な限り踏襲して、指導してきました。
始めて弓道を習うものに対してまずは10㎏程度の弓力の弱い弓を使い、素引きで弓道に最適な体の使い方を覚えさせます。同じように巻き藁稽古でも弱い弓を使い、両足・両腰・両肩の六根(ろっこん)と体の中心で構成される三重十文字で、体をまっすぐにすることを最重要にして稽古させます。次に、正しい手の内をつくらせて覚えさせ、大三に打起し手に余計な力が入らずに手の皮が巻き込まれ弓をひねる準備を覚えさせ、引き分けで弓手の角見の働きを繰り返し稽古させます。しばらく稽古してできるようになってくると次に馬手の働き、と重要な順に、基本をひとつひとつできるように段階を踏んで指導していきます。
まず、このような骨法の基礎を徹底的に身に着けさせる事を重要視して指導します。素引きと巻き藁稽古のみでも1-2年ほど稽古させると、弓力の弱い弓のまま、イーストン1913の細く軽いジュラルミン矢で初めて的前で引いても、弓手の角見の働きで離れ矢がまっすぐに飛び、羽分け程度で半分くらい的中するくらい、矢所が集まる程度の骨法の基本を身につけさせます。弓力の弱い弓で細い矢を飛ばすのは、射法訓原典の前段にあるように、ありとあらゆる弓射の問題が矢に伝わりやすく、細く軽い矢はバランスを失いやすいので実は初心者用の弓具セットで矢を真っ直ぐ飛ばして的中させるのは難しく、なかなかうまく的中しません。しかし、的中を狙うのではなく、的中は射の結果としてとらえ、的中した射としない射の射の振り返りをして、さらに自身の射を磨いていきます。弓手の角見の働きでまっすぐ矢を飛ばせるようになるのが骨法で、古来の射手がそうしていたように、素引き・巻き藁稽古だけでも十分な骨法の基礎を養うことができ、宮田純治は現代の弓道指導においても、古来の稽古法を意識して弓道指導を続けてきました。
堂射の射手の驚異的な弓射技術も、「射法訓」の「弓を射ずして骨を射る事最も肝要なり」とあるとおり、弓道の基本は骨法で、普段なにげなく行っている弓道稽古と同じ基本、ということになります。弓力の弱い弓を使用して、骨法を身に着けるために素引き・巻き藁稽古からスタートして長年稽古し基礎を固め、最終的にそのレベルに到達したことを知ると、また普段使っている弓具が堂射で生まれ、現在に至っているものと知ると、何気ない普段の当たり前の稽古にも、より弓具や射法の仕組みを理解し取り組むことができます。堂射の射と弓具の成り立ちを振り返る事で、堂射で生まれた弓具が現代まで使われている背景を知ることができ、弓道の射法の仕組みを深く理解し、普段の稽古に役立てる一助にもなるかと思います。
「紅葉重ね・離れの時機・弓具の見方と扱い方」(弓道範士十段 浦上栄 著 浦上直・浦上博子 校注)によると、四つ掛けのゆがけは、薬指にかけるために親指が長く曲がっている為、弓手起点の離れで弦枕から弦が外れた際に、親指部分の帽子に弦が触れて矢の方向性が変わるリスクを内包しています。堂射から的前の弓道に使用する為、従来通常の弓射である歩射で使われていた三つがけを堅帽子にして、親指の帽子が短く、中指に向かって四つがけよりも帽子の曲がりが少ない三つがけの堅帽子のゆがけに進化し、現代の弓道まで使用されてきたようです。その形状により弓力の弱い弓でも、帽子に弦が触れて矢の方向性が変わるリスクを軽減しつつ、馬手を固めて弓手起点の離れを実現する三つがけの堅帽子のゆがけが、弓道において一般的となったようです。
また、この堅帽子のゆがけの形状は、引き分けから離れの射法にも影響しており、四つがけと三つがけでは取りかける指の形状及び弦道の位置が違う為に、四つがけでは馬手をひねらず引き分けて離れ開くような形の残心となり、三つがけでは馬手をひねりつつ引き分け離れる為、その手の形がのこる残心となり、馬手の残心の形も異なるという、ゆがけの形状による違いがあります。詳しくは、弓道教本第二巻に詳述されています。ひとつ付け加えると、弓具を壊さない射を実現する正しい取りかけの重要なポイントとして、それは弓道を含む蒙古式取りかけ法共通の重要なポイントということですが、とりかけは以下の写真のように、矢の「の(シャフト)」一本分あけて、矢を人差し指に添えてとりかけます。

こう取りかけることで、会に至るまで筈と馬手の接触によるハズこぼれを防ぎ、人差し指で矢こぼれを防ぎますが、これは下記の動画で説明される通り、弓道を含む東アジアの蒙古式取りかけ法に共通した、弓射の物理現象に裏打ちされた大事なポイントになります。
矢ハズにくっつけてとりかけると、引いているうちに知らず筈を押し出し、少し押し出した状態、または完全に押し出したハズこぼれの状態(空ハズ)で弓射するリスクが高く、弓に破損につながる大ダメージを与える要因になります。その状態でハズを押し出さないよう力を入れると、馬手に力が入りのじないを起こしたり、弓手で離れる離れの障害となります。
間をあけすぎると、人差し指が矢に振れる面積が小さく、わずかな力みによる矢こぼれの可能性が高くなります。また親指の付け根で弦押しすることで親指が反り、弓手の角見の働きで弦が外れた際に離れも良くなります。堅帽子に弦が触れ矢の方向性が変わるリスクを軽減させる為に、浦上栄先生は更なるゆがけの改良を弽師の先生と共にされました。
浦上栄先生は三つがけのゆがけを、さらに的前射法に適した堅帽子のゆがけにする研究していらっしゃいましたが、その浦上栄先生が考案された的前用三つがけのゆがけを、弽師の千葉幸弘先生が浦上栄先生と長年研究開発され実現し、宮田純治もそのゆがけを使用しています。具体的には、三つがけの指の長さが短く中指に真っすぐ向かう特徴を生かし、帽子が真っすぐな性質で、ゆがけの親指と弦が十文字(横からではなく上から見た状態)なり、取りかけの弦押しで帽子が反り、弓手の角見の働きで弦が弦枕から外れた際に弦から軽く離れ、堅帽子のゆがけの弱点である、離れにおける帽子と弦・矢との接触問題を軽減したゆがけになります。
このように、弓道の射手と弓具製作者が、伝統の弓道を踏まえて、更に良くする為に様々な工夫がなされてきたことを知ると、ふだん何気なく使用している当たり前の弓道の弓具、伝統の射法についてもなぜそうなっているのか、その根拠・仕組みを深く理解する事ができ、普段の稽古も先人の叡智を感じることができて奥深く、味わい深いものとなります。
(出典)
・「堂射」入江康平著
・「射法訓」吉見 台右衛門(順正)
・「紅葉重ね・離れの時機・弓具の見方と扱い方」(弓道範士十段 浦上栄 著 浦上直・浦上博子 校注)
・「弓道教本 第二巻」公益財団法人全日本弓道連盟
・「7 Min Friday: Thumb Release Beginners Issues and how to fix them」Armin Hirmer