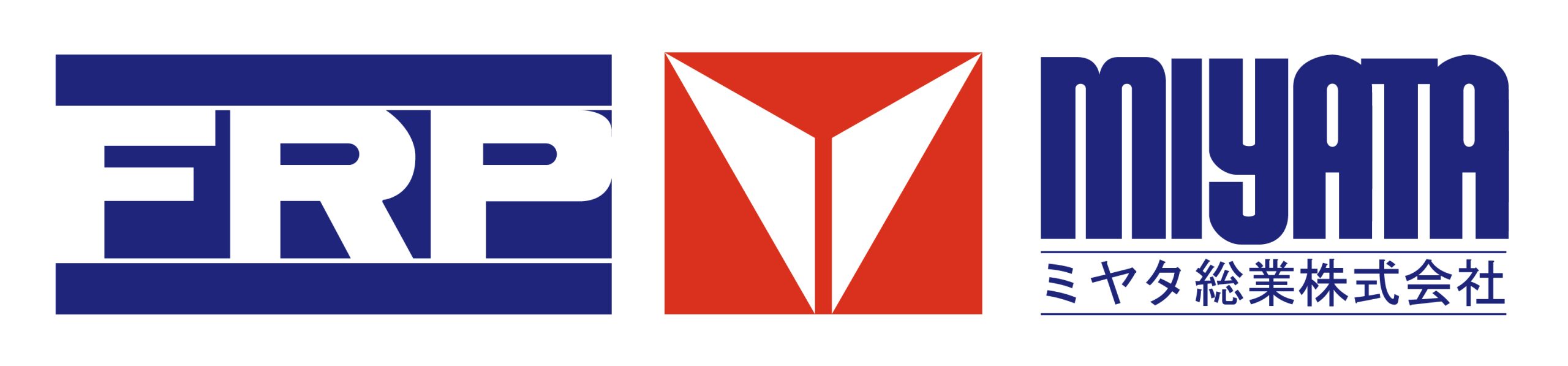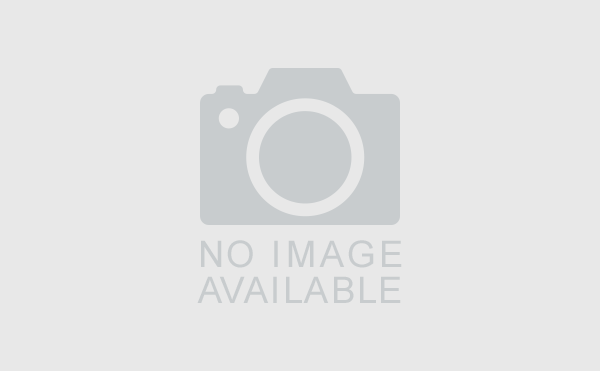弦音(つるね)とは何か
弓道においては「良い弦音(つるね)」は上級者の証である等、弦音が古来より良い弓射技術で引けている基準のひとつとして、重要視されてきました。その為、多くの弓引きの皆様が良い弦音を出す為にも、弓射技術を磨き、日々の稽古に励まれていらっしゃると思います。
しかし、実は良い弦音を出す為には、逆説的ですが弦音は気にせずに、骨法をはじめとした弓道の基本に忠実な射を心がけるほうが、結果として良い弦音を出す近道になる、物理学的な根拠があります。
その為には、まず弓道における「弦音」についてあいまいに理解するのではなく、「そもそも弦音とは何か」、正確な弓道における「弦音の定義」を理解し、どうして弦音が弓道において重要視されてきたのか、世界の弓射と異なるその弓道特有の弓射の仕組み・物理現象を理解する必要があります。
まず定義について、全日本弓道連盟公式ホームページにある「弓道用語辞典」の定義によれば、以下の通りに定義されています。
弦音(つるね) Tsurune
離れで,弦が弓の額木・「姫反」を打って発する音のこと。
The sound made at Hanare when the Tsuru hits the Hitaiki (Himezori).
弓道用語辞典 公益財団法人全日本弓道連盟
https://www.kyudo.jp/howto/terminology.html
弦音が弦が弓を打って発する音であることは万人の弓引きの皆様がご存じであるところですが、この定義で最も重要なのは、その音は、上関板の額木だけではなく、同時に「姫反り」を打って鳴る、という点です。もちろん、弓把は高く(弦は短く)張った状態である事が前提になります。
単に上関板を打って音が鳴るだけであれば、これは弓道だけではなく、他のアジアの弓でも音が鳴ります。上関板と弦の相打ちの間の距離が狭ければ、弦が戻り切った際にその反動で弦が弓を打つので、どのような引き方でもなんらか音が鳴るのは、以下のアジアの弓での弓射動画で確認できます。弓返りしない射法(弓道を含むアジア共通の射法のカトラ・テクニックで弓はひねっている)でまっすぐ弦が返っても、相打ちとの距離の近さにより弦が反動で弓を打ち、やはり弦音のような音が鳴っている事でもそれがわかります。
しかし、弓道の「弦音」とは姫反りに弦が当たり鳴る、ということは、相打ちよりもずっと弦との距離が離れている姫反り部分で弦が当たらないとなりませんが、弓道の和弓で弓返りしない射、または弓返りしても弓返りが遅く弦が弓よりも先に返ってしまう引き方で引くと、弦との距離が大きく離れている和弓の姫反り部分には、その引き方では弦は当たりません。姫反りに弦が当たる為には、大三から鋭く弓をひねりながら弓を引き分け、会でめいいっぱい弓と弦が張り詰めた状態から、更に角見の働きで上押しの力を加えつつ弓を捻り、その効果で弦枕と弦道にかかった弦が外れたと同時に、勢いよく弓が回転する必要があります。そのような弓手起点の離れで弦が離れたと同時に弓が鋭く回転すると、回転している状態の弓に弦が当たる為、上関板と同時に姫反りに弦があたります。そして、弓道でいうところの、大きく澄んだ「弦音」が鳴ります。
以下は、左が宮田純治使用弓(使用弦:麻弦、悪射で弦切れする程度の柔らかめの合成繊維の弦)で、右が硬質の弦で2,000射以上射こんだ弓になります。弓手起点で離れることができると、このように相打ち部分の関板だけではなく姫反りに弦跡が残り、離れの際に鋭く澄んだ弦音を発します。
一見、右の弓の方の姫反り部分のほうが大きく塗装が剥げているので、鋭い角見が利いているようにみえますが、これは硬質な弦の特性によるもので、ヤスリで削られたようにFRPがむき出しになっています。これをみても、硬質な弦が弓に与える影響の一端が確認できます。また、左側の宮田純治使用弓に綺麗に一様に中央についている姫反り部分の弦跡に比べると、右寄りに弦跡がついていますが、これは相対的に角見の働きが弱い為になります。麻弦・柔らかい合成繊維の弦を使用し、弓手起点の鋭い角見を利かせることができると、左の宮田純治の弓の姫反り部分の弦跡のような状態になります。弦が柔らかければ、そのように引けなくても、馬手離れの際に弓に与えるダメージを軽減できます。

これらの弦と弓が返る動きは非常に高速である為、肉眼で確認することが困難になります。その為、弓手で離れ、高速の弓返りをした証として、姫反りに当たって鳴る鋭く澄んだ弦音、そしてその結果として姫反りに均一に残るその弦跡が、弓道では「弦音」として、良射の証として高く評価されてきたことが、弓射の物理的な動きを理解することでわかります。姫反りに弦跡が残っていても、上下左右に大きくブレて弦跡がついている、側木に弦が当たっている場合は、弓把が低く弦が長く、弦が不安定な状態で姫反りを含む弓に当たっている可能性があります。
「竹林射法七道」によると、「釣合が悪くて離れたなれば弦に騒ぎがあって弦音は悪くきこえるものである。」との説明があります。これを物理現象として説明すると、「弦に騒ぎ」とは、弓手・馬手のバランスが悪く馬手で放すと、弦が大きく左右に振れる状態を指しています。その射では弓返りしない、または弓返りが遅く姫反りに弦が当たらない為弦音も良くない、ということになります。つまりこの伝統の教えは、高速度カメラが無い時代でも、弦音の良し悪しによって弓手で離れられたかどうかがわかるという、物理現象の真実を踏まえた教えであることがわかります。
また、正面打起し射法の源流である本多利実先生の口述伝「弦音について」によると、「深く説明するまでもなく、弦音は弓弦を引き張りて離すときにおこる音であります。・・・(中略)・・・関板に弦がつきすぎている(弦と上関板の距離が近すぎて、その為弦音が良くない)のも、皆弦音によって知ることができます。」
弦と上関板の距離が近すぎるのは弦が長く弓把が低い為であることも多く、その状態は様々な弓射の問題を起こす要因となります。
その為、下記の記事でご説明したとおり、上関板と弦との相打ちの距離は「弓道の弦音」とは関係が無く、むしろそれが開いている下が強く伝統の尾州成の弓が「弦音の良い弓」として重宝されてきたことは、上記の弓道の弓射の物理現象を確認することで理解できます。
弓道範士十段 故 浦上栄 先生は、この弓返りの現象を当時政府機関の協力のもと、120分の1秒程の高速度カメラを使って、自身の弓射で弓手起点で離れた時の離れの瞬間、弦と矢が分離する瞬間の写真をおさめています。そのコマ送りの離れの写真は、「紅葉重ね・離れの時機・弓具の見方と扱い方」の著書で確認できます。会でやごろに達し、以下の通り浦上栄先生の説明でそれぞれの瞬間の写真に説明が加えられていますが、「角見の働きにより弦が弦枕からはずされた瞬間」の写真、「矢と弦が分離する寸前」で弦と同時に弓が鋭く返っている瞬間の写真など、肉眼では速すぎてとらえられない瞬間の写真が確認できます。当時高速度カメラは非常に高額で一般に入手するのは困難で、この弓射の瞬間の撮影は政府機関の協力を通じて実現した貴重な資料になりますが、現在は科学技術の発展に伴って、当時よりずっと高速の数千分一秒の高速度カメラが、一般にも入手できる金額で世に出るようになりました。その為、一般にも徐々に馬手離れと弓手の離れがどのように違うのか、 弓・弦・矢がどのように動くのか、どのような射が弓に衝撃を与えるのか、逆に与えないのか、高速度カメラのリアルな映像・コマ割りの写真により、より身近に解明されていくと思われます。
上記の通り、そもそも「弦音とは何か」という弦音の定義、「弦が姫反りに当たり鳴る音」という事実を認識した上でないと、上関板に弦を当てるのみで弦音を出そうとして、相打ちの幅を狭める為弓把低く弦を長めに張るなどの誤った工夫をしてしまう場合があり、これは弓射に良くないばかりか、弓が不安定な状態になり、弓がひっくり返ったり、破損につながる弓を痛める要因ともなります。古来の標準の握りの位置より高くする事も、相打ちの幅を狭めますが本来の弦音とは関係が無く、また弓把等の握りの位置との相対距離で弦の長さを決める場合、握りの位置を高くして同じ弓把で弦を張ると実際には弦が長くなり、様々な問題を起こす事は、下記の記事で説明しています。
弦音は、弓手で離れ鋭い弓返りの結果として出るものである為、宮田純治や、兄弟子に当たる稲垣源四郎先生も指導に際しては、弓返りや弦音はまず気にしないよう、手の内を始めとした弓道の基本のプロセスを、地道に稽古する指導をしてきました。この指導は逆説的に見えますが、良い射の結果としてでる高速の弓返り、弦音、という物理現象としての事実をとらえると、理にかなった指導であります。
弓返りを焦り、弓手を緩めたり無理に弓返りさせたりしても弓手の離れよりずっと遅いスピードでしか弓が返りませんが、それでも肉眼ではそれなりに高速にみえるので、かなり熟練しないかぎり、その判断は目でとらえるのがなかなか難しいものです。その為、古来より良い射の結果を、「弦音」という音と、姫反りに残る弦跡(高い弓把=短めの弦、が前提になります)で判断してきたことは、当時高速度カメラが無かった時代、非常に合理的な判断基準と思います。詳しくは、以下の記事にてご説明しておりますので、ご高覧いただければと思います。
(出典)
・「弓道用語辞典」公益財団法人全日本弓道連盟公式ホームページ
・「紅葉重ね・離れの時機・弓具の見方と扱い方」(弓道範士十段 浦上栄 著 浦上直・浦上博子 校注)
・「竹林射法七道」(小林治道述)
・「Do You Even NEED Khatra? | Asiatic Archery」(Nu sensei)