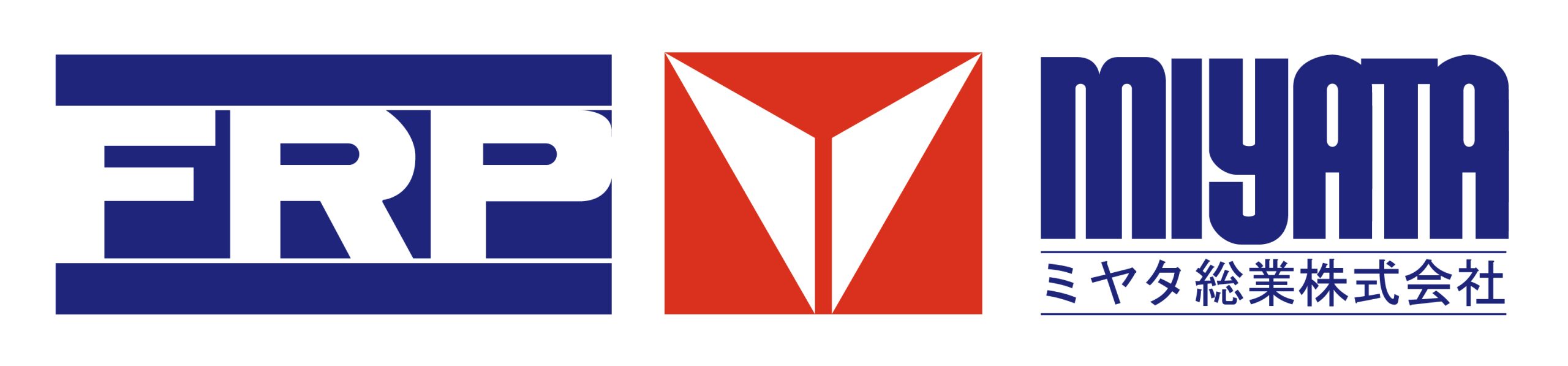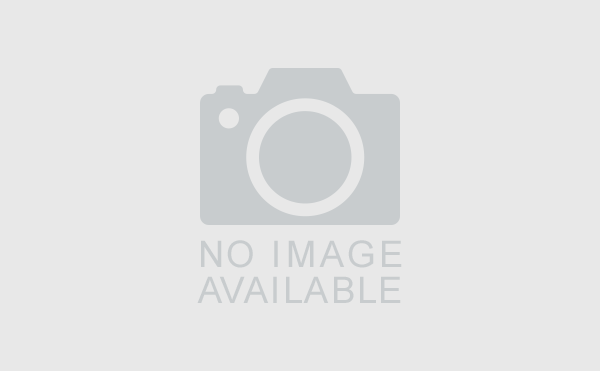グラスファイバー弓とは何か
竹弓に対して、グラスファイバー弓は省略して「グラス弓」と呼称されていますが、弓本来の性質を表す、「竹弓」の対義語としての正確な表現では、「FRP(エフアールピー)弓」と言います。まず竹弓は、ヒゴと呼ばれる竹を素材にした芯材に、内側、外側に竹を張り付け、木材を側木・関板に使い製作したものであります。そしてグラス弓は、竹弓の竹ヒゴの代わりに、木材で製作された部分を芯材に使い、この内竹、外竹の部分に、FRP(Fiberglass Reinforced Plastic)と呼ばれる、「繊維で強化されたプラスチック板」を張りつけて製作されたものです。
つまり、「竹弓」も竹だけではなく木材も使用され、グラス弓も、FRPと木材により製作されたものであり、竹弓の「竹」も、グラス弓の「グラス」も、材料の一部分、特に内竹・外竹部分の材料から名前がとられています。「グラス(グラスファイバー)」とは「ガラス繊維」のことで、このグラス(ガラス繊維)そのものはグニャグニャと柔らかいものですが、樹脂に繊維を入れて固めると、樹脂が強靭化され、かつ反発力・弾性力が高くなる、という素材特性があります。これは古代から知られている科学技術で、漆でも繊維を入れて固めると強靭化される性質が古来より知られており、科学技術の技法として存在します。
つまり現代の科学技術も、何か突然変異で人工的に合成されたものが生み出された、というものではなく、古来から人類の叡智として発見された古代の科学技術を元に、産業革命以後、人工的に生成された物質が生み出されてきた背景があることを知ると、竹弓の延長線上に、FRP弓(グラスファイバー弓)が存在することがわかります。そのうえで、それぞれの特質の差を知ることが、道具の性質を良く理解することにつながります。
「樹脂(じゅし)」とは、もともとは植物から分泌される樹液(松ヤニ、漆等)が硬化した物質を表す言葉ですが、石油等から化学的に合成されるプラスチック等も「樹脂」というくくりで「合成樹脂」という表現が用いられてきました。これが、現代のグラスファイバー弓・合成弓(FRP弓)、合成弦(合成繊維の弦)について、正確に、かつ本質的に理解するポイントになります。接着剤も、現在は竹弓を含めてこの合成樹脂の接着剤を使用しており、この「合成弓」という表現方法では、広義には多くの竹弓も「合成弓」になってしまいます。
以下は、FRP、グラスファイバー繊維テープの一例。現在、様々なFRPが存在し、ホームセンター等で購入できるグラスファイバー繊維のテープを合成樹脂で固めて、FRPと似たような物質を製作することもできる。

※左からグラスファイバーFRP、カーボンファイバーFRP、グラスファイバー繊維テープの一例。これに限らず、世の中に様々なタイプのFRP・グラスカーボン繊維素材が存在する。グラスカーボン弓とは、内竹・外竹の代わりに、FRPを使用した弓の呼称であり、正確には「FRP弓」と言う。
「合成弓」という用語も、グラスファイバーFRP弓の呼称として長年使われていましたが、グラスファイバー弓の本質を表す正確な用語ではなく、「何の合成なのか」、を正確に表現した説明を加えると、「合成樹脂」、つまりプラスチックになります。「合成弓」をいったんより正確な表現に書き直すと、「合成樹脂弓」になりますが、これではただの「プラスチック弓」になってしまいまだ正確な表現ではなく、「FRP(Fiber Reinforced Plastic):化学繊維で強化されたプラスチック」と正確にFRPを表現すると、「FRP弓:化学繊維(グラスファイバー・カーボンファイバー)で強化された合成樹脂(プラスチック)の弓」、ということになります。
この正確な定義では呼び名として長く複雑すぎて一般的には浸透しにくく、「FRP(エフアールピー)弓」も、日本人には発音しづらく、やもえず以下の記事でご紹介したとおり、弊社も昔広告などで「グラスファイバー弓」と表現していた事情もございます。
つまり、「グラス弓」の「グラス」という言葉、「合成弓」の「合成」という言葉は、言葉の本来の意味を示す原型をとどめないほど省略されてしまっている為、その用語をあいまいに受け取ってしまうと実態がわからず、弓具の取り扱いを誤る恐れがあります。弓の本質を理解する為には、このように元々の意味をたどる必要があります。
なぜこのような少々堅苦しい「グラスファイバー弓」の定義をいまさら説明するのか、その必要があるのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、正確な用語を用いたり、弓道・弓具の用語の意味や本質を正確に理解することは、正しい弓射や弓具の取り扱い上でも、非常に重要になります。それは、言葉の正確な意味を理解していないと、誤った認識の下で誤った対応することになってしまうからです。「グラス弓」も誤った認識のままだと、グラスカーボンFRP弓も、それぞれの弓によって大きく性質が異なるのに、「グラスカーボン弓」とひとくくりにあいまいな理解をすることで個々の弓の取り扱い方法を誤り、弓に不具合を出してしまったり、正しい弓射ができない恐れすらあります。
ひとくちにグラスファイバーFRP弓といっても、上記の定義の通り、内竹・外竹部分に非常に反発力高く強靭なFRPが使われていますが、中の芯材部分は木であります。その芯材の木の性質で、弓の性質そのものが大きく異なります。以下の記事でご説明した通り、機械での自動ムラ取りの為に硬い木の芯材を使ったグラスファイバーFRP弓と、しなやかな木の芯材のグラスファイバーFRP弓では、性能・性質が全く異なります。前者は硬い弦をかけて空ハズを出しても壊れにくい、という性質があっても、後者は、内竹・外竹部分のFRPの強靭さはありますが、芯材のしなやかさは、むしろ竹弓に近いものがあります。
このように、正しい用語の認識を持ち、正確な弓具についての理解ができないと、グラスカーボン弓と竹弓、という2分類によるあいまいな認識で、「竹弓は(正しい取り扱いの上で正しい弓射をしたとしても)壊れやすい」、「グラスカーボン弓は(切れない弦でも空ハズでも)壊れない」、といった、誤った認識をもってしまうことにつながります。
弓道の弓射の物理的な本質は、「世界一エネルギー効率の高い弓射」であり、正しい弓具の取り扱いの上で、正しく弓射できると、会の状態で溜まった大きな位置エネルギーを、余すところなく矢を飛ばす運動エネルギーに変換される為、そもそも弓にダメージを与えるエネルギーが残りません。弓が破損するということは、エントロピーの法則・エネルギー保存の法則により、矢に乗り移らなかった使用不可能なエネルギーが、弓に大ダメージを与えている為です。
悪射は初心者はもちろん、上級の射手を含めて、どのような射手にもでるものです。悪射がでても切れない弦を用いると、その悪射が出た時のエネルギーのロスを、全て弓に与えてしまう事になり、弓の破損につながります。第一に重要な事は、弓に合った適切な弦を使うことが重要であり、そして、竹弓だろうとグラスカーボンFRP弓だろうと、「離れを弓に知らせぬぞ良き」の弓射で、弓を破損しない正しい弓射をせねばなりません。ミヤタがグラスファイバーFRP弓を初めて開発するまで、弓道には竹弓しか存在しなかったわけで、竹弓がすぐに壊れてしまう性質なのであれば、そもそも実用・武道の用をなしません。以下の記事でご説明したとおり、堂射では誤った取り扱い・弓射ではあっという間に弓具が破損してしまうような強いエネルギーを持つ、非常な強弓の竹弓を用いて、一日に数千射から一万射以上まで矢数をかける、弓射競技が実際に行われていた事実があります。これも、麻弦を切らず、竹弓を壊さずに引く正しい取り扱い・正しい弓射で引いている為に、実現していました。
「合成弦」という呼称も、言葉をそのまま受け取っても、用語を正しく解説した説明が無いと、意味がよくわかりません。弦は元々は植物の麻から作られた麻弦が基本であり、その後、化学製品である合成繊維から作られた、合成繊維の弦がアーチェリーで作られ、以下の記事でご説明したとおり、宮田純治が1967年に初めて弓道用に合成繊維の弦を用いて、弓道にも合成繊維の弦が使われるようになりました。このように、「合成弦」とは、正確には「合成繊維の弦」を意味します。
これらは産業革命以後の科学技術で製造された合成樹脂や合成繊維が導入された明治以後の時代に、竹弓や漆の樹脂を「天然素材」のものが当たり前とされていた当時の背景を踏まえ、漆などの天然素材の樹脂は「天然素材の」という表現が省略され、産業革命以後でてきたプラスチック等の「合成樹脂」、ナイロンやケプラー等の「合成繊維」、これらの用語から「樹脂」や「繊維」の部分が省略されて、「合成」だけが用語として残り、「合成弓」、「合成弦」という言葉が浸透してきた経緯があります。樹脂も繊維も、「天然素材」と「合成素材」が存在し、お互いの対義語であることを理解していないと、グラスカーボンFRP弓も、合成繊維の弦についても、正確な理解が難しくなり、取り扱いを誤るリスクがあります。
言葉の定義を正確に理解することは、弓具だけでなく、弓道そのものにおいても、「離れ」、「弦音」、といった弓道の用語を正確に理解する上でも重要であることは、以下の記事でもご紹介しております。弓具、弓道の定義を正確に理解することは、物事の本質を芯から捉え、弓具を傷めず自身も安全に、矢勢よく的中良い射につながります。
(出典)
・「堂射」入江康平著
・「漆塗の技法書」十時啓悦・工藤茂喜・西川栄明